
皆さんこんにちは。
里得木です。
今回は「青銅と鉄 固定電話と携帯電話」というインパクトのある(?)タイトルで書かしていただきます。
僕のおかしな価値観の一部を理解していただければ光栄です。
まず、人間が使っていた道具の歴史を紹介します。
最初の頃は、石器を使っていました。
打製石器(石同士をぶつけて鋭くしたやつ)とか磨製石器(石同士をこすり合わせて鋭くしたやつ)って呼ばれるものです。
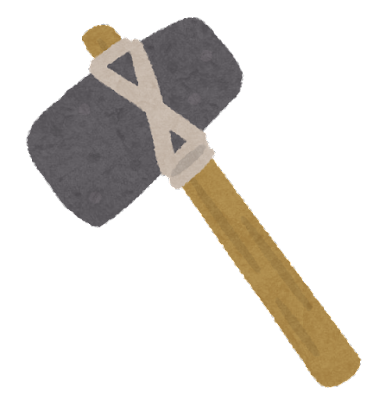 (https://www.irasutoya.com/より引用)
(https://www.irasutoya.com/より引用)
次に、青銅器が使われるようになりました。
青銅器に使われている青銅は銅に錫(すず)を10%程度混ぜて作るそうです。
そのため、加工が容易で「メソポタミア・エジプトでは紀元前3500年ごろから青銅器の開始がはじまる。」(青銅器 - Wikipedia)と書かれるほど昔から使われていました。
 (https://www.irasutoya.com/より引用)
(https://www.irasutoya.com/より引用)
やがて、鉄器が使われるようになりました。
鉄器はその名前の通り鉄でできています。
青銅より硬い鉄は様々の場面で活躍しました。
鉄の加工はかなり難しく、「最初の鉄器文化は紀元前15世紀ごろにあらわれたヒッタイトとされている。」(鉄器時代 - Wikipedia)のように青銅器の普及から2000年も経ってから普及しました。
しかし、それ以前でも隕石などから鉄を得ていたという情報もありました。

(https://www.bing.com/images/create?FORM=GDPGLPより引用)
このように書くと、日本でも「青銅器→鉄器」の順番で使われていたと思うかもしれません。
ところが、同時に大陸伝わり、使われ始めた時期もほとんど一緒なのです。
その結果、軍事や農耕などの面では鉄器が使われるようになりました。(青銅器は美しい見た目から、お祭りなどに使用されたそうです。)
似たような現象(本来の文明の発達速度に合わずに海外から技術が伝わる現象)がアフリカでも起きていたので、取り上げてみました。
下の表が固定電話の普及率の表です。
どの国も低いことがわかります。
ちなみに、日本は何%だと思いますか?答えは記事の最後で!

(https://www.soumu.go.jp/g-ict/item/phone/index.htmlより引用)
次に、携帯電話の普及率です。2014年時点で8割を超えています。

(https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h27/html/nc123120.htmlより引用)
普通の文明では、固定電話が普及して、携帯電話が普及するという流れをたどることが多いです。
しかし、急激に発展したアフリカでは、電話回線の工事の大変さや、利便性、格安の中古の2Gスマホ流入などの影響で携帯電話のみが普及していという状況になっています。
青銅器と鉄器、固定電話と携帯電話。
似たような状況と言えるのではないでしょうか?
読者登録お願いします。
クイズの答え
ちなみに、日本の固定電話普及率は66.5%(全体では66.5%・20代世帯では9.5%…固定電話の保有状況(2022年公開版)(不破雷蔵) - 個人 - Yahoo!ニュース)です。